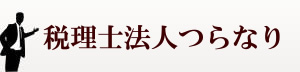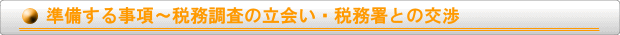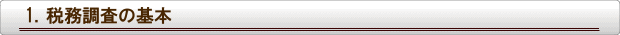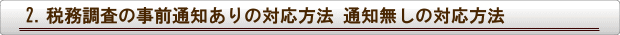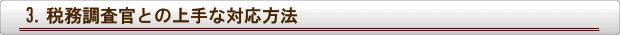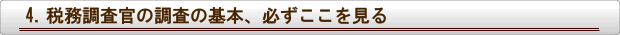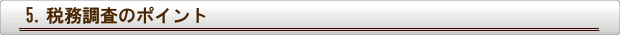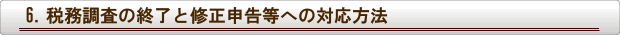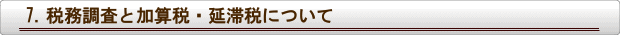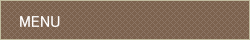- トップ
- 税務調査対策支援について
税務調査と聞くと嫌なイメージを持っている方がほとんどだと思います。
法人の社長様や事業主様にとって、できれば来てほしくないというのが本音でしょうが、調査を完全に拒否することは困難です。
弊社では、調査が円滑に行われるよう、経験豊富な税理士が責任を持って税理調査に立会わせていただきます。
 専門家のノウハウを使い、効率的な事前準備のお手伝いをさせて頂きます。
専門家のノウハウを使い、効率的な事前準備のお手伝いをさせて頂きます。
 税務署・都道府県・市区町村の税務調査に全面的に立ち会わせて頂きます。
税務署・都道府県・市区町村の税務調査に全面的に立ち会わせて頂きます。
 税務調査の立会い終了後の税務署等との交渉も対応致します。
税務調査の立会い終了後の税務署等との交渉も対応致します。
 お客様の利益が損なわれないよう、認められるべき正当な会計処理等については、お客様の立場に立って税務署等に主張致します。
お客様の利益が損なわれないよう、認められるべき正当な会計処理等については、お客様の立場に立って税務署等に主張致します。
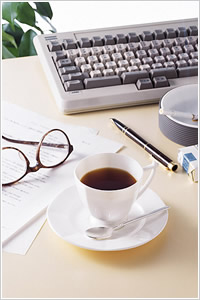
税務調査は納税者が提出した申告書の内容が、正しいかどうかを確認するために行われるものです。ですから、必要な帳簿書類を記帳・備え付け、それらを基に申告していれば、何も怖れることはありません。
事前準備で全ての対策をするのは時間的に現実問題になかなかできません。
そこで、税務調査官がどの辺を重点的に調査をしてきそうかをあらかじめ把握したうえで、実際には、そこに的を絞って事前準備をしていくことになります。
下記に事前準備する内容は記載していますが、やはり不安かと思います。
文章ではお伝えできない、実践で培った職人技のような、ポイントもございます。
事前準備を行うにあたって、私共税理士の専門知識を使い、より効率的に事前準備のお手伝いをさせていただければと思います。
税務調査は事前準備がとても大事です。まずは、税務調査とはどんな事をするのか?基本から再度確認しておきましょう。

- 税務調査の基本
- 税務調査の事前通知ありの対応方法 通知無しの対応方法
- 調査官との上手な対応方法
- 税務調査官の調査の基本、必ずここを見る
- 税務調査のポイント
- 税務調査の終了と修正申告等への対応方法
- 税務調査と加算税・延滞税について
■ 税務調査には「強制調査」と「任意調査」がある。

●強制調査とは:裁判所の令状により、国税局査察官(マルサ)が大口で悪質な脱税等に狙い定めて行う税務調査です。
●任意調査とは:納税者が提出した申告書や集められた資料情報などに基づいて税務署内で行う「机上調査」と、税務調査官が納税者の事務所や店舗などに出向いて行う「実地調査」があります。一般的は税務調査とは、この「実地調査」のことで、納税者に同意・確認しながら進められる税務調査です。通常は、税務署から事前に調査日時の通知があります。
■ 納税者の義務と、税務調査官の権限と義務
●納税者の義務⇒受忍義務
納税者の権利を不当に侵害するような調査でなければ、税務調査官の質問に対して応えなければなりません。また、求めに応じて、帳簿やその関連資料を開示して内容等を説明する義務があります。これを「受忍義務」といいます。
一方的に調査から逃げ続けたり、質問に応えることを拒否し続けたりした場合は、最終的に罰則を受ける可能性があります。
●税務調査官の権限と義務⇒質問検査権と守秘義務・秘密保持義務
税務調査官には、納税者に対して様々な質問をすることや、帳簿や関連資料等の開示を求めることのできる「質問検査権」が与えられています。ただし、税務調査官は国家公務員ですので「守秘義務」があり、加えて、税務調査によって知り得た納税者のプライバシーや会社の営業上の秘密等に関しても「秘密保持」の義務が課せられています。
秘密を漏らしたり、盗用したりした場合は罰せられることになります。
税務調査は、通常、予期しない時に実施されます。ただし、一般的には、事前に税務署から通知が有り、納税者、顧問税理士(会計事務所)の都合等を確認して、調査日程が決定します。
1- 税務調査の事前通知があった場合の対応

●「顧問会計事務所と相談の上でご返事します」と応える
●税務調査官の氏名と担当部署と、できれば調査理由を聞く
●その後、私ども税理士事務所に連絡する
税務署から「×月×日に調査にお伺いします」との事前連絡があった時には、即答は避け、「顧問税理士と相談の上でご返事したい」とお応えください。税務調査官の氏名と担当部署(できれば調査理由も)を必ず聞き、私ども税理士事務所に連絡を入れてください。私どもと、日程の調整をした後、税務署に連絡をして調査日を決定します。
2- 税務調査の事前通知が無い場合の対応

●身分証明書、質問検査章の両方の提示を求める
●その後、私ども税理士事務所に連絡する
●調査の開始は税理士が来るまで待ってもらう
●やむを得ない理由があれば調査の延期を求めることが可能
事前通知なしで「現況調査(※)」に来る場合もあります。調査官は、写真付きの身分証明書と調査権限を示す質問検査章を携帯していますので、両方を提示してもらい税務署員であることを確認し、私ども税理士事務所に連絡を入れてください。そして、私ども税理士が到着するまで調査の開始を待ってもらうように打ち合わせてください。
もし、経営者や経理担当者がいない場合や、冠婚葬祭、重要な商談などで、対応できない時には、その事情をきちんと税務調査官に説明して、調査の延期を相談してください。その後、私ども税理士と相談して調査の日時等を決定しましょう。
3- 机・カバン・金庫等の中の調査
●納税者の同意無しに調査することはできない
●やましい点がなければ、机・カバン・金庫等の中は見せるべき
任意調査においては、納税者の同意を得ずに調査官が、机やカバンや金庫等の中を調べることはできません。しかし、調査官は、机やカバンや金庫等の中にあるものも含め、会社内にある全ての経理資料等は質問検査権の対象であるとの前提でいます。不自然に拒めば、あらぬ疑いをかけられることになります。やましい点がなければ、開示して調べて頂きましょう。
4- 自宅調査
●納税者の同意無しに調査することはできない
●やましい点がなければ、従容として案内すべき
調査官は、調査に必要な物(ブツ)が自宅にあることが分かった場合でも、納税者の同意を得ずに、自宅への臨場はできません。やましい点がなくても、調査官を自宅へ招き入れることの抵抗感は理解できます。しかし、ここは従容として案内しましょう。
5- 書類等の貸し出し
●業務に支障がない範囲で、貸し出しに応じる
●調査官が書類等を預かる場合には、必ず預り証が手渡される
調査官から、帳簿類等を税務署に持ち帰って検討させて頂きたいとの要請を受けた場合、業務に支障がないのであれば応じましょう。困る場合には、その旨をはっきり告げましょう。無理にとまでは言わないはずです。その部分のコピーを取るなり、後日改めて借りにくるなり、何らかの対応を取ることでしょう。
6- お茶や食事はどうすれば良いか
●お茶は、常識程度に出せば良い
●食事の用意をすることは、全く必要ない
調査官は、調査先が気を利かして食事を用意しても食べないように指導されています。ただし、常識的な範囲のお茶やコーヒー等であれば用意してもかまいません。
■税務調査官との対応の基本
●調査の最中は自然に応対することが一番のポイント

●質問に対しては常に誠実に応え、誤りは素直に認める
●必要以上にへりくだったり、高圧的なったりしない
●落ち着きなく目線を動かさない
●聞かれてもいないことを細かく説明したりしない
何も不正が無くても税務調査は嫌なものです。精神的な負担は大きく、イライラすることもあると思います。調査官からの質問に対し、必要以上にへりくだったり、高圧的になったりなったりしないように気をつけましょう。常に誠実に応え、もし誤りを指摘された場合は、素直に認めることが必要です。言うは易くかもしれませんが、普段と変わらぬ自然な応対を心がけましょう。
■実地調査の留意点
●調査官は疑問点を解決するために、帳簿・関連書類等の開示を必ず求めます
実地調査では、調査官が抱いている疑問点に応えれらる帳簿や関連書類を示すことができれば、何ら問題はありません調査官の要請にすぐに応えられるよう、整理・保管をしっかりしておきましょう。また、祝い金や交際費などで、現金で支出し領収書が無いものについては、支出相手や日時などの内容を必ず書き留める習慣をつけることが必要です。
①現金決済が多すぎないか
②仕入の水増しはないか
③売上の計上漏れはないか

④経費の水増しはないか
⑤固定資産やたな卸資産の動きに不自然な点はないか
⑥源泉徴収漏れはないか
⑦借入金や貸付金におかしい点はないか
⑧売掛金や買掛金に疑問点はないか 等
1- 現金の調査
●現金商売の場合は、調査当日の金庫などにある現金保有高と現金出納帳の残高をチェックする
●現金売上の除外はないかをチェックする
●現金支出で領収書がないものをチェックする
●役員に対する仮払金をチェックする
●端数のない金額の支出で、しかも同じ相手先との取引があった場合の内容をチェックする 等
★現金調査の対応策①現金残高は日々確認し、現金出納帳を必ず記帳しておく
②領収書、請求書、見積書、契約書などの整理・保存を確実に行う
③事業に関係のない書類や個人の現金は金庫等で保管しない
④仮払金精算等の書類を整備する
⑤役員による立替金の精算は、請求書や領収書の提出が必要
2- 預金の調査
●預貯金の得意先勘定、手形勘定、有価証券勘定などとの振替関係をチェックする
●銀行残高証明書が添付されているかどうかをチェックする
●銀行残高証明書と帳簿の残高とを照合する
●担保不十分な借入金がある場合、別途預金や簿外資産がないかなどをチェックする
●むやみに多くの、あるいは遠隔地の銀行口座がる場合等の理由をチェックする
★預金調査の対応策①銀行残高証明書と帳簿残高が一致していない場合には、預金勘定調整表で内容を明確にしておく
②個人名義の通帳・印鑑などは保管しないこと
③自社振替の小切手の裏書したもの(引き出し)については、その使途を明確にしておく
④個人的な借入金については、貸借契約書等を作成する 等
3- たな卸の調査
●期末たな卸資産の過去との妥当性をチェックする
●たな卸資産を過小評価していないかをチェックする
●実地たな卸を行って算定基礎が明確であるかをチェックする
●たな卸資産の評価額計算の基礎となる取得価額の正否をチェックする
★たな卸調査の対応策①決算期末に正確なたな卸を心がけ、算定基礎を明確にしておく
②仕入単価の改訂や仕入割戻しの処理は正しく行っておく
③加算すべき付随費用は、必ず取得価額に加算しておく
④期末近くの仕入や売上返品は、必ず売上か在庫に計上する
⑤たな卸資産の評価方法は、税務署へ届け出た方法と一致しているかを確認しておく
⑥外注や受注については、材料をどこが負担するのかを契約書などで明確にしておく 等
4- 売上の調査

●売上計上漏れがないかをチェックする
●送り状や請求書、売買契約書などの証拠書類と商品在高をチェックする
●売上割戻しの計上時期や交際費に該当するものはないか等をチェックする
●月別や前年同期と比較し、著しく増・減している場合は、その理由や原因をチェックする
●現金売上については、その売上計上が正しいかどうかをチェックする
●期末前後の”期ズレ”売上がないかを必ずチェックする
★売上調査の対応策①送り状や請求書などの日付は正確に記入し、未記入にしない
②返品商品は適正な価格で、たな卸資産に計上しておく
③商品在高がすでにないのに、売上が翌期の日付になっていないかを確認しておく
④領収書がレジによる記録であるか、手書きによるものかを明確に区分しておく
⑤売上計上基準を明確にして、継続して適用しているかを確認しておく
⑥売上高が期末に減少し、翌期首に増加している場合などは、利益調整とみられる可能性があるので、その理由を明確にしておく 等
5- 仕入の調査
●水増し仕入がないかをチェックする
●月別や前年同期と比較し、著しく増加している場合、架空仕入等の有無をチェックする
●実地たな卸に際しての原始記録等をチェックする
●評価損・廃棄損計上の妥当性をチェックする
●仕入原価が正しいかどうかを、仕入諸掛に係る証拠書類などによってチェックする
●仕入割戻しについて、関係証ひょう書類を突き合わせてチェックする
●翌期の仕入が当期に繰上げ計上されていないかをチェックする
●簿外売上のための簿外仕入はないかをチェックする
★仕入調査の対応策①仕入と売上商品・たな卸商品を突き合わせておく
②期首商品(製品)たな卸高に期中の仕入(生産)を加えて、期末たな卸高を差し引いた売上原価を正しく算定しておく
③仕入原価に、商品を取得するために直接要した費用を算入しておく
④仕入割戻しが正しく行われ、仕入価格が適正であるかを確認しておく
⑤仕入計上時期が適正であるか確認しておく 等
6- 外注加工費等の調査
●架空計上などの費用がないかをチェックする
●外注加工費請求書と外注依頼書、下請計算書などを照合してチェックする
●材料が支給されたかどうか、材料費支払経理がどうなっているかをチェックする
●たな卸関係がどなっているかをチェックする
●外注工賃を現金で支払った場合は、領収書の真実性をチェックする
●小切手支払については、振出欄の支払先と実際の支払先とを照合チェックする
★外注加工費等の対応策架空労務費や架空材料費などの疑いを抱かれないように、労務者の実務日数確認のためのタイムカードや材料費を確認するための納品書を正しく管理する
②現金支払については、現金出納帳と領収書が合っているかを確認しておく
③支払手形が、実際に支払われた相手先と一致しているかを確認しておく
④前払金を出す場合や前払いの決済が長期間されていない場合などは、理由を明確にしておく 等
7- 役員給与等の調査

●定期同額給与等の要件を満たしているかをチェックする
●個人が負担すべき支出が会社の経費として処理されていないかどうかをチェックする
●接待交際費などの名目で支出した金銭の領収書の有無や内容をチェックする
●海外渡航費などの旅行目的、海外出張報告書、旅費・支度金等の内容をチェックする
●個人名義のゴルフ会員権や社交団体の入会金、会費などもチェックする
★役員給与等の対応策①個人的支出に認定されると、損金不算入の役員賞与扱いになり、法人税・所得税でのダブル課税となりますので事前に内容を確認しておく
②役員給与の中には、経済的利益も含まれていることに留意する
③ゴルフ会員権を個人で所有する場合や社交団体の個人会員である場合は、経費や会費などを交際費で処理していないことを確認しておく 等
8- 交際費の調査
●本来交際費であるものが他の科目で処理されていないかをチェックする
●固定資産やたな卸資産の取得価額の中に交際費に該当するものが含まれていないかをチェックする
●交際費支出で、役員の個人支出なのではないか、会社業務のための支出なのか等、使途をチェックする
★交際費等の調査の対応策①交際費でない他科目で処理している場合は、その内容を明確にできる書類を整備しておく(会議費・売上割戻し・販売促進費・福利厚生費・広告宣伝費・旅費交通費・会費寄付金等の科目を再度チェックしておく)
②飲料関係の領収書は、料飲の目的・人名・人数等が明確になっているかを確認しておく
③得意先・仕入先接待の際のタクシー代を忘れずに交際費に計上しておく
④年末等の贈答品の取扱では、単価・個数・贈答先リスト等を作成しておく
9- 人件費の調査
●架空人件費の計上はないかをチェックする
●特殊関係使用人(家族等)に対し過大な給与を支払っていないかをチェックする
●非出社の特殊関係人等に対する給与を、会社従業員給与と仮装して支給していないかをチェックする
●期末における未払い賞与の計上があればその内容をチェックする
★人件費の対応策①給与台帳、源泉徴収簿、タイムカード、社員名簿、履歴書等を整備・保管する
②就業規則、給与規定、賞与規定、旅費規程、退職金規定、役員退職金規定等を整備する
10- その他の調査
修繕費の調査●修繕費の中に減価償却すべき資本的支出に該当する支出はないかをチェックする
●修繕費の計上時期は妥当かをチェックする
●架空の修繕費の計上はないかをチェックする
寄附金の調査●親・子会社間や関連会社間等の取引価格は妥当か、個人的費用はないか、計上時期は正しいか等をチェックする。
敷金・保証金の調査●不動産賃貸業務等において、賃借人からの預かり敷金や保証金の償却金額に関し、その売上計上時期が、適正かをチェックする
消費税の調査本則課税申告の場合
●課税・非課税区分が多く混在する経費科目の内、福利厚生費、旅費交通費、通信費、交際接待費、諸会費等を重点的にチェックする
簡易課税申告の場合
●売上高、家賃収入、雑収入等の収入面全体と資産の売却等を詳細にチェックする
印紙税の調査●課税文書に該当する契約書を重点的にチェックする。適正な金額の印紙が貼られているか、貼り忘れはないか。また、消費税の記載方法による税額の違いはないか等とチェックする。
実地調査が終了しても、まだすべてが終わったわけではありません。税務調査官は、税務署に帰ってからもよく吟味し、資料を線密に分析します。その結果、納税者の申告に全く問題がない場合は「是認通知書」を発行し(実際には発行されていないケースが多い)、問題がある場合には、「修正申告の慫慂(しょうよう)」を行ってくるのが一般的です。
1- 税務署の指摘に従う場合は、修正申告をする
修正申告とは、簡単に言えば「間違っていることを認めて、納税者が自ら申告を直す」ことです。「慫慂(しょうよう)」というのも難しい言葉ですが、要するに「強制はしませんが、修正申告をした方がいいですよ」と納税者に勧めることをいいます。これに応じる場合は、税務署の指摘に沿って税額を計算し直し、「修正申告書」を作成・提出した上で、不足分の税額と加算税を納めることとなります。
2- 修正申告の慫慂に応じない場合は、更正・決定を受ける
大抵の納税者は修正申告に応じることで一件落着となるのですが、中には税務署の指摘にどうしても納得ができない、という人もいるでしょう。修正申告の慫慂を黙殺した場合、当然税務署は第二段階として、「更正」あるいは「決定」という行政処分に出てきます。これは、「税務署の指示に従い、〇〇円の不足税額と加算税を支払いなさい」という命令です。このとき、青色事業者に対しては必ず「更正・決定の理由附記」を行わなければならないこととされています。その理由を呼んで、納得した場合には更正に応じることになります。
3- 不服申立て・提訴する場合でも、とりあえず税金は払ってしまう

しかし、それでも納得できず、税務署と争ってでも払いたくない場合には、「不服申立て」という手続きに入ります。税務署長への異議申立て、国税不服審判所への審査請求を行い、それでも主張が認められなければ、裁判所に提訴することになります。しかし、税務調査に絡む争いでは、納税者の主張が全面的に認められたケースは、ほとんどありません。この場合に気を付けなければならないことは、不足税額と加算税には「延滞税」(こちら参照)がついてしまいますので、税務署と争う前に、とりあえず納税したほうが得だということです。結果的に主張が認められれば、支払ったお金は返ってくるので心配は要りません。
税務調査で誤りを指摘された場合、修正申告等をしなければなりません。その場合、不足税額等を納めるだけでなく、一種の罰金のような「加算税」と「延滞税」が課せられます。
加算税の種類
①過小申告加算税
②無申告加算税
③重加算税
①過小申告加算税申告した税額が少なかった場合
●税金を期限内に申告・納付した後、税務調査で誤りが指摘され、正規に納めるべき税額より申告した税額が少なかったときに課されます。
過小申告加算税の税率はこちらを参照ください。
②無申告加算税期限までに申告しなかった場合
●期限内に申告書を提出しておらず、後に税務調査等でそのことが発覚した場合に課せられます。
無申告加算税の税率はこちらを参照ください。
③重加算税帳簿を偽造したり、故意に売上等を隠したりした場合
●税金を少なくするために、故意に帳簿を偽造したり、売上を隠したりした「仮装・隠ぺい」が発覚した場合に課せられます。
重加算税の税率はこちらを参照ください。
延滞税
法定納期限までに税金を納付しなかった場合
●期限内に税金を寄付しなかった場合、「延滞税」の対象となります。通常、税務調査は3~5年間さかのぼって行われますので、金銭的負担は、大変大きなものになります。
延滞税の税率はこちらを参照ください。
【加算税・延滞税についての表】
利子税・不納付加算税については割愛しました。